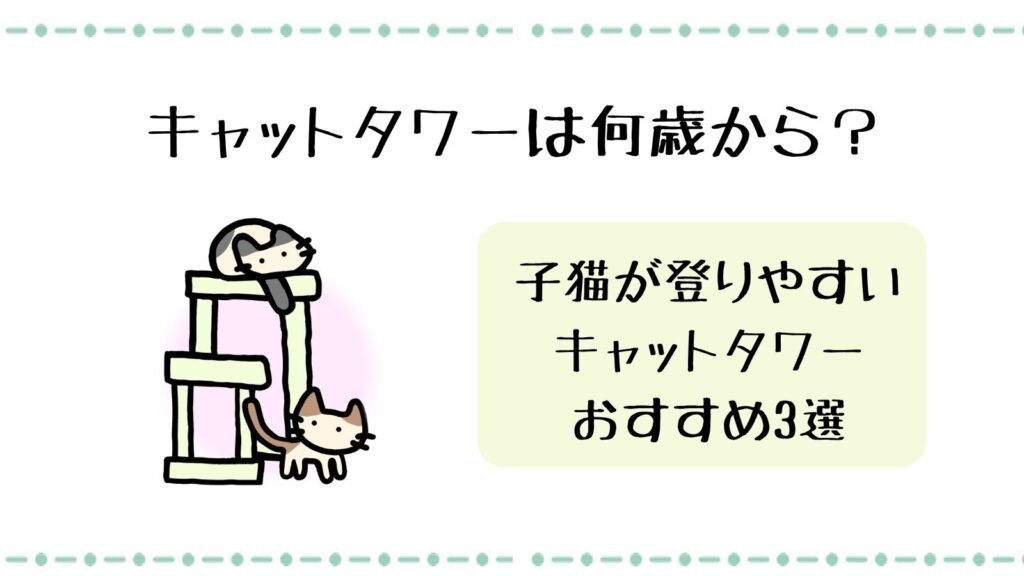
かわいい子猫の飼い主のみなさん、
「そろそろキャットタワーを使いたい」「でも安全に使えるのはいつごろからなのかわからない」と悩んでいませんか。

キャットタワーは何歳から使えるの?

子猫にキャットタワーは危ないのでは?
そこで、子猫にキャットタワーを使わせてもよい時期、を調べてみました。
その結果、キャットタワーは生後3ヶ月(12週)頃から使用可能ということがわかりました。
この記事では、キャットタワーを使い始めるタイミングや、安全に使わせるためのポイント、おすすめ商品を紹介します。
「キャットタワーって何歳から使えるの?」「まだ早いかも?」と不安な方も、この記事を読めば安心して準備ができますよ。
子猫が楽しく、安全に暮らせる環境を整えるために、ぜひ最後までご覧くださいね。
百聞は一見に如かず!!楽天の特集ページならキャットタワーの種類、特徴、カラー、人気ランキング、関連アイテムがわかりますよ!
キャットタワーは何歳から?子猫が登りやすい低めのタワーおすすめ3選
キャットタワーは何歳から使えるのか月齢の目安について解説します。
それでは、詳しく見ていきましょう!
キャットタワーの使用は生後3ヶ月がひとつの目安
子猫にキャットタワーを使わせるタイミングとして、生後3ヶ月(約12週)が一つの目安とされています。この頃になると、運動能力や筋力がしっかりしてきて、ジャンプ力もだいぶ安定してくる、というのがその理由です。
実際に飼い主さんたちからも「3ヶ月を過ぎてからキャットタワーに興味を持ちはじめた」という声が多く見られます。
とはいえ、すべての子猫に当てはまるわけではなく、個体差もあるので、まずは様子を見ながら低めのタワーからスタートするのが安心です。
ケージのような囲い付きのタワーなら、最初の練習にもぴったりですね!
生後2ヶ月はまだ早い?注意すべき理由
生後2ヶ月の子猫は、まだまだ身体が小さく、骨も柔らかい状態です。この時期に高い場所へ登らせてしまうと、落下したときに骨折などの重大なケガにつながる可能性があります。特に好奇心が旺盛な子猫ほど、無茶なジャンプや飛び降りをしやすいので要注意です。
この月齢では、まずは「平面での遊び」や「小さな段差を上り下りする」くらいから慣らしてあげるのがベストです。
高い場所に登りたそうにしていても、焦らずに安全第一で見守っていきましょう。
子猫の成長に合わせたステップ導入がポイント
キャットタワーを使い始めるときに重要なのは、「段階的にステップアップする」ことです。いきなり高いタワーを与えるのではなく、まずは床から30cm〜50cm程度の低いタワーから始めましょう。
成長に合わせて、60cm、90cm、そして1メートル以上へと徐々に高さを変えていくと、子猫も無理なくタワーに慣れていけます。途中で滑りやすくないか、爪とぎ部分がしっかりしているかもチェックポイントです。
焦らず少しずつ慣らしていけば、子猫自身も「登るのが楽しい!」って思ってくれますよ。
子猫にぴったりなキャットタワーの選び方
子猫にぴったりなキャットタワーの選び方について解説していきます。
ポイントを押さえて後悔のないタワーを選びましょう。
高さはどれくらいがベスト?
子猫に合ったキャットタワーの高さは「60cm以内」がひとつの目安になります。この高さなら、万が一落ちてしまっても衝撃は少なくて済みますし、ジャンプ力がまだ弱い子猫でも登れる安心設計です。低めのタワーでも、複数の段差がついているものなら運動量も確保できるので問題ありません。
反対に、いきなり120cm以上のタワーを使わせると、踏み外したときのリスクがかなり高くなってしまいます。
まずは「見下ろせる場所がある」「登れる段差がある」というバランスで選んであげてくださいね。
足場の幅とステップ間隔は広めが安心
キャットタワーの足場の広さは、子猫の安全性を左右する重要なポイントです。足場が狭すぎると、バランスを崩しやすくなり、滑って落ちる原因になります。おすすめは「直径30cm以上の足場」がついたタワーで、これくらいあると子猫が体を丸めてリラックスできる広さになりますよ。また、ステップ間の距離が10〜15cmほどであれば、小さい体でも無理なく上下できます。足元がしっかりしていると、子猫も安心して動けるので、自然とタワーを好きになってくれることが多いです。
組み立て式 vs 完成品、それぞれの特徴
キャットタワーには「組み立て式」と「完成品」の2種類がありますが、それぞれにメリットとデメリットがあります。
| タイプ | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 組み立て式 | ・自宅に合わせてカスタマイズ可能 ・パーツ交換がしやすい | ・安定感に欠けるものもある ・ネジが緩むと危険 |
| 完成品 | ・すぐ使える ・安定性が高い | ・大型で場所を取る ・配送が大変な場合も |
子猫用なら「安定性がある完成品」または「しっかり固定できる組み立て式」がおすすめです。
成長を見越した拡張性もチェック
タワーを選ぶときに意外と見落としがちなのが「成長後も使えるかどうか」です。子猫の時期だけ使えるサイズでは、すぐに物足りなくなってしまってもったいないですよね。最近は、拡張パーツがあるタワーや、途中で棚板を追加できるタイプなども増えていて、こうしたモデルなら長く使えてコスパも良好です。また、体重に耐えられる設計かどうかもチェックポイントです。「成猫になっても使える設計です」と記載されている商品を選ぶと、安心して長く使えますよ。
子猫から使えるキャットタワー・おすすめ3選
おすすめの子猫用キャットタワーを紹介します。
キャットツリー・KITTEN
ふかふかの生地を使用した安定感のある据え置きタイプのキャットタワーです。
支柱をカスタマイズして高さが変えられるので、小さい時は低めに、大人になったら高めに、さらにシニアになったら低めに戻すといった使い方ができますよ。
>>カスタマイズパーツの専用ページを見てみる(楽天市場)
思い切り爪とぎできる糸巻き支柱になっていて、ハンモックも気持ちよさそうです。
猫壱・バリバリボウルタワー
猫ちゃんたちに大人気、すり鉢状のつめとぎベッド・バリバリボウルが2段になったバリバリボウルタワーです。すり鉢状のベッドを段ボールの枠組みにセットするだけで完成。もちろん、しっかり固定するためのロック機能付きです。つめとぎボウルは交換可能ですから長く使えるのもうれしいですね。
Mau・タワーシニアベイス
階段式のキャットタワーで、ゆったりサイズのステップ台、台の段差はすべて26㎝以下の低段差設計です。子猫だけでなく、足の短い子、身体の大きい子、シニアなどどんなネコにも使えるよう、ねこの使いやすさにこだわった作りです。
キャットタワーを使い始める時のコツと慣れさせ方
キャットタワーを使い始める時のコツと慣れさせ方についてご紹介します。
「使ってくれない…」と悩む前に、慣れさせ方のコツを知っておきましょう!
初日は低い場所から遊ばせる
キャットタワーを初めて設置した日、いきなり子猫が最上段に登ることはまずありません。最初は「低い段」「土台部分」から慣れてもらうのが大事です。新しい物に対して警戒心を持つ子も多いので、まずはタワーの近くに寝かせてみたり、足元におもちゃを置いて様子を見ましょう。子猫が「これ、なんだろう?」と好奇心を見せてくれたらチャンスです。そのまま無理に手を出さず、見守ってあげると自分から近づいてくれるようになります。
おやつやおもちゃで興味を引く方法
なかなか登ってくれないときは、「おやつ」や「お気に入りのおもちゃ」で誘導するのが効果的です。例えば、ステップの上にちゅ〜るを少し乗せたり、鈴のついたじゃらしをゆっくり段ごとに移動させてみましょう。子猫がそれを追って登っていくようになれば大成功です。無理に引っぱらず、あくまで「遊びながら導く」ことがポイントです。成功したら「すごいね〜」「よく登ったね〜!」と声をかけてあげると、どんどん自信がついてくれます。
無理に登らせない・見守る大切さ
登らせたくて、つい抱っこして最上段に置いてしまいたくなる気持ち…分かります。でも、これは逆効果です。怖い思いをすると、「キャットタワー=怖い場所」と認識されてしまって、次から近づかなくなってしまいます。あくまで子猫自身のペースで、「ここは安心できる」「登ってみたいな」と思わせることが重要です。信頼関係をベースに、好奇心を刺激するのが慣れさせる一番のコツです。
少しずつ高さをアップしていくステップ方式
「登るのが楽しい!」と感じてもらえたら、次は少しずつ高さをアップしていきましょう。低い段だけで遊んでいる時期があっても大丈夫です。タワーのレイアウトを変えたり、日によって違う段におやつを置いたりして、「ちょっとずつ上に挑戦」する動線を作ってあげましょう。あくまで自然な流れで、子猫が「今日はここまで登れた!」と達成感を感じられるようにしてあげるのが理想です。この成功体験の積み重ねが、タワーを「楽しい場所」と思わせてくれますよ。
まとめ|キャットタワーは何歳から?子猫が登りやすい低めのタワーおすすめ3選
キャットタワーは生後3ヶ月ごろから徐々に使えるようになりますが、子猫の運動能力や性格、安全設計のタワーかどうかで判断することが大切です。段差や素材の安全性をしっかり確認して、無理のないステップアップを心がければ、子猫でも安心して楽しめますよ。焦らず、子猫のペースに合わせて楽しく導入していきましょう。
より安全な環境を整えたい方は、獣医師のアドバイスやレビュー評価もあわせてチェックしておくと安心です。猫に関する詳しいガイドは、環境省「猫の適正飼養ガイドライン」も参考になります。
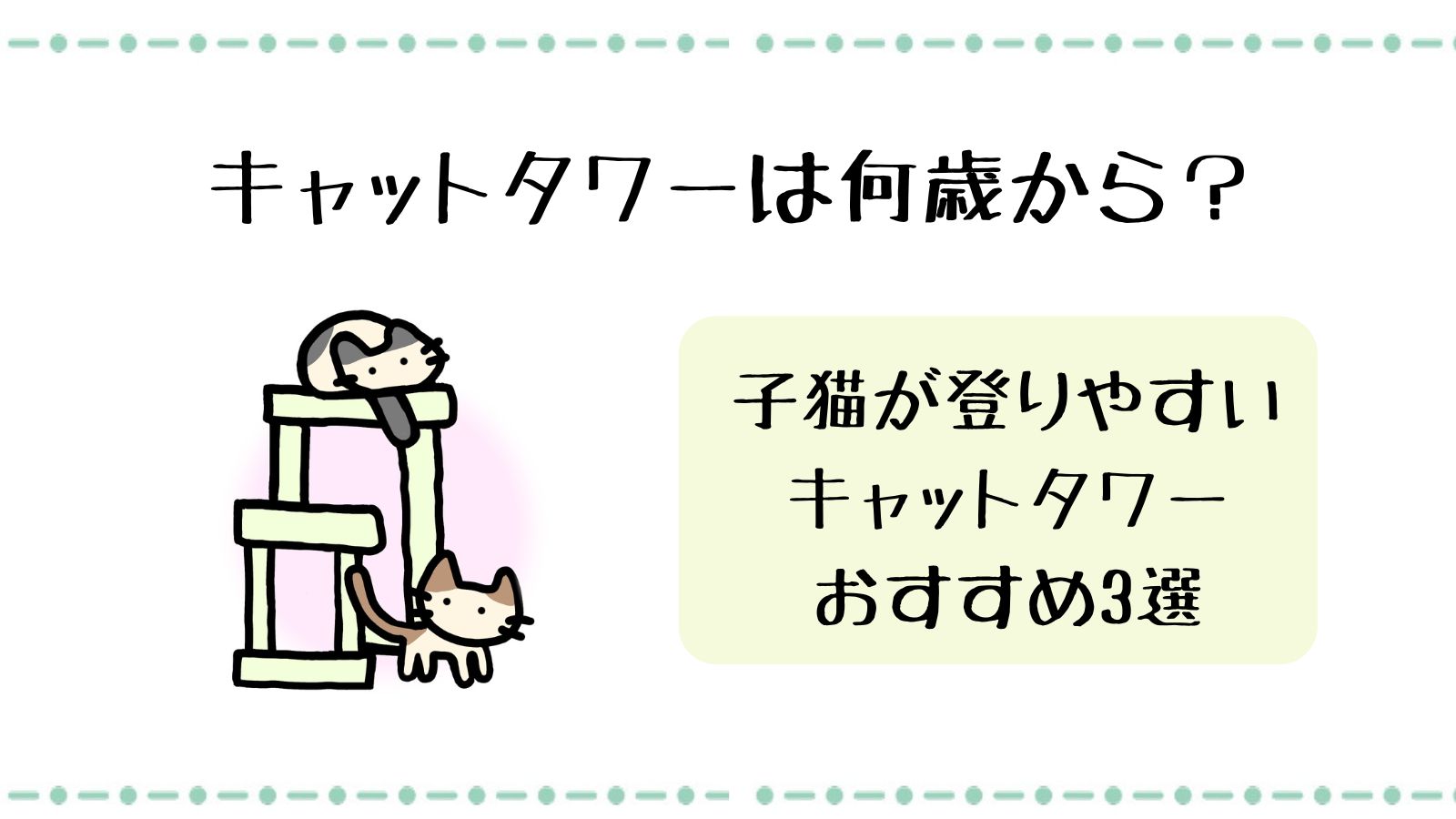







コメント